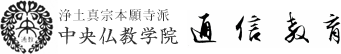通信教育卒業生が主となって各地で学習会が開催されています。在学中だけではなく卒業後も学びを深めていくことができます。また、同窓会誌『法の友』を毎年お届けし、全国の同窓会支部の活動報告や、“生涯学習”の一助となるコンテンツの紹介を行っています。

法の友 令和6年7月1日発行
インドネパール仏跡参拝旅行記
令和5年専修科卒業 大川 千鶴子(79歳)
行きたい!と思っていたインド仏蹟参拝の10日間の旅に行くことが出来ました。ベテランの添乗員さんと現地のインド人のガイドさん、どちらも良い方で良かったです。
行程はベナレス→サールナート→ダメーク大塔→ベナレス→ガンジス河→ブッダガヤ→尼連禅河→スジャータ村→ラージギル→ナーランダー仏教大学→ラージギル→バイシャリ→クシナガラ→ルンビニ園→祇園精舎というコースでした。どの遺蹟も想像を絶する物。
二千五百年の時空を超えて迫ってきます。ブッダガヤでは、祈りの渦の中に居ました。世界中の人々が、お釈迦様お一人の一点に集中し、その真理に納得しているようでした。
私は、祇園精舎にて、二千五百年前に、ここにお釈迦様が立たれて、法を説かれていた地点に立ちました。この時、身近に釈尊を感じ、釈尊と隣り合わせに居るような錯覚に襲われました。不思議な一瞬でした。
釈尊は、きっと時空を超えて私達を護り続けて下さっているのであろうと思いました。
インド・ネパールの旅を思い切って決断して良かったです。一生涯の財産となりました。同行の皆様、添乗員の奥村様、現地のシャルマさん、本当にありがとうございました。
中央仏教学院で学ばせてもらって本当に良かったと、心より感謝しています。
合掌
矢代 静子
「インド・ネパール仏跡巡拝の旅」の案内が届き、開いてみると“ガンジス河の沐浴風景の見学”が目に飛び込んできました。ガンジス河は、私がずっと行ってみたいと思っていたところなのです。早速、娘に相談したところ、「行ってきたら」と気持ちよく勧めてくれました。
娘は、中央仏教学院に在学中にインドに連れて行っていただき、ガンジス河の風景にとても感動したことから、私の気持ちを分かってくれたようです。
パスポートが来年5月で切れることもあり、「もう、今しかない」と思い、即申し込みました。
旅行3日目、ガンジス河に向かう道を歩いているだけでも信じられないのに、ガンジス河の風景が目に入ってきたときには、何も言えず胸が熱くなりました。船から見る町の風景に心を奪われつつ、蝋燭に火をともしたお皿を「ナマンダブツ」と称えながらガンジス河に浮かべました。
娘は、「自分の時も奥村さんという添乗員さんやったと思う」とずっと言っていました。帰って写真を見せたところ「やっぱり!」と言ってとても喜んでいました。親子2代でお世話になりました。
そして、今回、旅行を共にした皆様方には、大変お世話になりました。ありがとうございました。
山本 知都子
明日は日本へ帰る、という最終日、私たちは祇園精舎の遺構で阿弥陀経のお勤めをしました。2500年前お釈迦様が1250人の大比丘に向かって話された阿弥陀経はどのように人々の心に流れて行ったのか。2500年経ってパーリー語から漢訳され、それをまた日本語読みされた「如是我聞」。お釈迦様、あなたの偉大な広大な、不可説不可称不可思議の教えを実感したい、と私たちはやってまいりました。
ラージキルの霊鷲山でのお勤め経験も感動的でした。頂上の小さなスペースで私たちが日本語でお勤めをしているとき私たちの後方では韓国の方々がその言葉でお勤めをなさり、また少し下の小さな祠からはスリランカのお勤めがながれ、そのリズムも音調も異なる声が不思議な一体となり、お釈迦様がかつて本当に立たれていたところに響いていきました。
インドに来て一番の収穫はお釈迦様を、多くの尊者・菩薩と呼ばれた人々を、現実の人として身近に感じられたことでした。竹林精舎が、スジャータ河が、お釈迦様の歩かれた道が、目の前に浮かぶようになったことでした。
ただ、インド国民の貧しさも忘れられないことの一つです。IT先進国といわれているインドの何と貧しいことか。未だにポンプで水を汲み、はだしで歩く子供たち。ぼこぼこの自動車道。汚れたシャツを着て埃の中で働く人々。
お釈迦様、見ていらっしゃいますね、これがインドだと。
宇ノ木 累子
決めた!インドに行こう!仏跡巡拝の旅に出よう!中仏の同窓会の旅の通知に私は飛び付いた。「お父さん、インドに行くよ」仏壇の写真に話しかけた。主人の三回忌を済ませ、これからの自分の生き方を考え始めた矢先のことでした。腰痛の為、旅行ケースはコンパクトに詰め込んだ。各県から集まった御同朋の皆さん七名と共に羽田空港を出発した。
機内では、私の右隣にインドの人が座っていた。「フロム、インド?」単語を並べて聞いた。彼は笑顔で「イエス」と答えた。スマホや手振りで会話が弾み、すっかり打ち解けた。ひと足先にインドに近づいた気分だった。
待望のデリー到着。インドは日本の九倍もの国土を持つ。この広大な地をお釈迦様は八十余年の生涯をかけて行脚された。その御苦労は想像を絶する。ホテルから仏跡地まで毎日バス移動すること2~4時間という過酷なものでしたが、実際にお釈迦様が説法して歩かれたであろうこの場所に私は今立っているのだと思うと、嬉しさで疲れも吹き飛んでしまいました。お釈迦様にゆかりのある世界中の人々が仏前に伏し、座して朗々と経を唱えておられる。私たち八人も中に加わり重誓偈をお勤めしました。各々熱のこもったお勤めの中、千五百年もの時を経てなお、尊敬され、親しまれているお方の事を思うと感極まり涙が溢れて声も途切れてしまいました。
長いようで短かった十日間、やさしく接して下さった添乗員様、そしてこの企画に関わられた皆様方、このような機会を私に与えて下さり真にありがとうございました。
合掌
下村 貞治
古代インドのバラモン教では人生を四つに分けて、それぞれのステージに即した生き方が幸せな人生を送れる理想的な生き方とされました。その四つとは?
1.「学生期」・・・8歳~25歳頃迄。 青少年時代で、心身を鍛え学習し経験を積む時期。
2.「家住期」・・・25歳~50歳、又は定年まで。社会人の時期で、就職・結婚・家庭を持ち子育ての時期。
3.「林住期」・・・50歳~75歳頃迄。 家族や社会的な義務とも離別して林の中で修行・瞑想する。つまり俗世間の掟に縛られず自分の内面と向き合い「本当の自分とは?」を考える段階。
4.「游行期」・・・75歳以降。 人生の終焉に向け準備をする時期(終活)この様な徹底した生き方は到底困難ですが、それに近い生き方をしたいと私は40歳に差し掛かった当たりから「四住期」の生き方に共感して、それを仏教に求め歩んできました。
その仏教の中でも浄土真宗の聖典「末燈鈔」には、「浄土真宗は大乗の中の至極なり」と示され、又「弥陀和讃」には、「久遠の昔に成仏された法身の弥陀が、この娑婆世界の凡愚を憐れんで釈迦仏となってガヤ城に応現し給う」と示されます。
そして親鸞聖人は「唯信鈔文意」の中で、釈迦仏は喜びを与え、教え導く慈父であり、阿弥陀仏は私達の苦悩を抜き救う悲母であると示して下さいました。 私は、この法の父(釈尊)であり、母(阿弥陀仏)である二尊が、私をこの「四苦八苦」という迷苦の世界から教え導き救って下さった事への御恩報謝の気持ちから、自分が元気なうちに どうしても仏跡を辿り参拝したいと思い今回の「インド・ネパールの仏跡参拝の旅」へ参加させて頂きました。どの仏跡聖地での参拝も「慈父・悲母」の仏さまを心に思いお勤めさせて頂きました。 今は長年の思いが叶いホットしているところです。
これからの残りの人生も、この貴重な仏跡の旅をただ思い出に終わらせる事無く「二尊の慈悲心」を後進にお取次ぎすべく歩んでまいりたいと思っております。
最後に、この仏跡参拝の旅を共に過ごして下さった法友と、最初から最後まで親切にご案内して下さった添乗員(奥村様)の方に心より感謝致します。 又、9日間にも渡り仏跡地へバスで連れてって下さった運転手・助手の方にも感謝致します。有り難うございました。
(ダンニャワード)
但木 秀徳
昨年の9月に中央仏教学院の学習課程を修了しました。卒業し同窓会に入会させていただきました。一年後インド・ネパール仏跡巡拝の旅の案内が届きました。テキストで釈尊の生涯については学びましたが、知識の上のことで釈尊その人には迫れない感覚がありました。せっかくのチャンスなので直接インド、ネパールに行き釈尊の足跡を訪ねることは意義があると思い参加しました。
①釈尊はどこで生まれ、②どこで修行され、③どこで悟りを開き、④どこで説法され、⑤どこで亡くなられたかという釈尊のご生涯について、その仏跡を巡ることによって知りたいと思ったのです。内藤知康著『どうなんだろう?親鸞聖人の教えQ&A』という本の中に「親鸞聖人は、お釈迦さまは私たちを救うために阿弥陀さまがこの世界にお姿を現わされた方といただいておられる。お釈迦さまはそのまま阿弥陀さまなのです」とある。釈尊を知ることは阿弥陀さまを知ることに通じる。初転法輪の地サールナート、釈尊成道の地ブッダガヤ、釈尊説法の地(霊鷲山)、釈尊涅槃の地クシナガラ、釈尊誕生の地ルンビニ、祇園精舎スラヴァスティーなどで「讃仏偈」、「重誓偈」などのおつとめをさせていただきました。そして南無阿弥陀仏をお唱えさせていただきました。阿弥陀さまが「我にまかせよ、必ず救う」と六字名号に込められたおはたらきを頂いた思いがしました。この旅の為にお世話になりました皆様に本当に感謝を申し上げます。